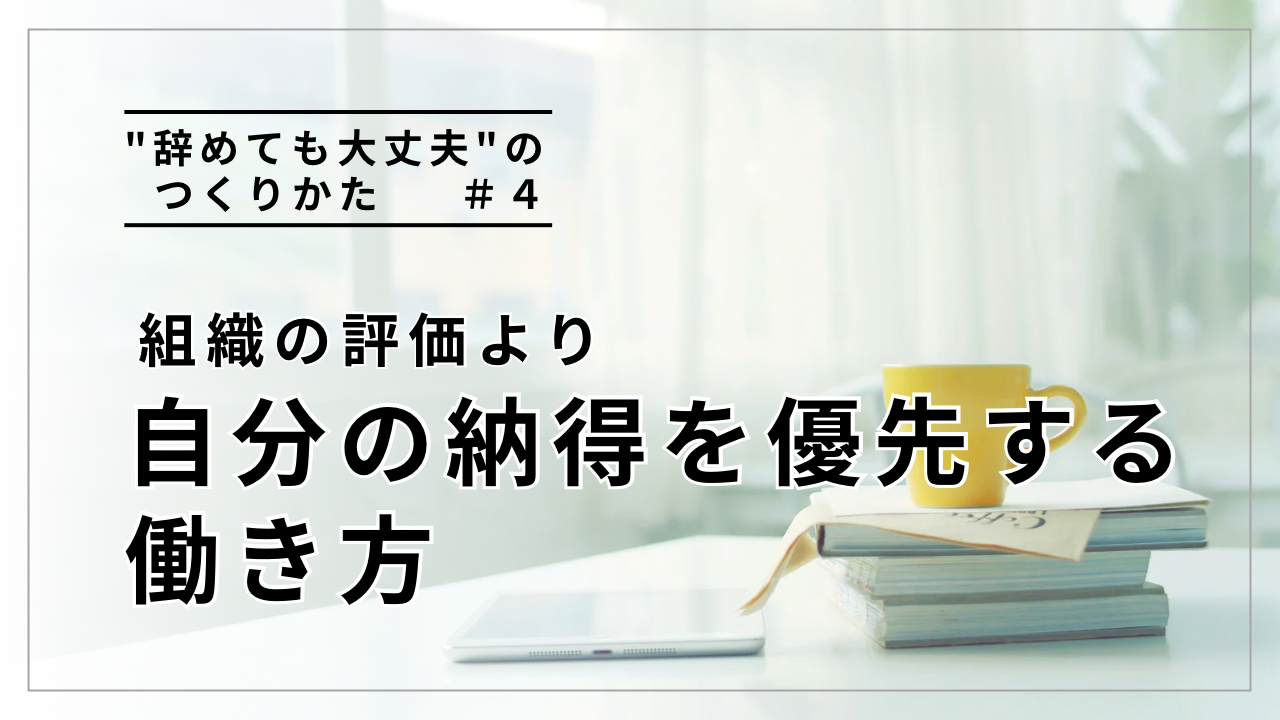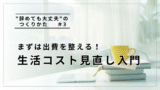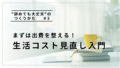──「組織に貢献する」。でも。
組織に尽くしているのに…評価されてる?
仕事に一生懸命取り組んできて、ふと考えてしまうことはありませんか。
「この努力は、正当に評価されているのだろうか?」
上司、部下、同僚との信頼関係があれば、大変な仕事でも、やり遂げたあと達成感を感じることができます。
ただ、どれだけ効率的に業務を進めても、提案を重ねても、自分の達成感と組織の評価が一致しているとは限らない・・・のが現実です。

制度は守り?それとも枷?
筆者は地方公務員として25年働いてきました。この公務員を例にしますね。
時間効率よく成果を出す人も、そうでない人も、基本的には同じ給与。
もちろん、年功序列や身分保障のおかげで、誰もが安心して働ける。それは確かに制度の大きな強みです。
ただ、**「もっと貢献したい」「もっと工夫を試したい」**と感じる人、つまり組織のために “めちゃ頑張ってる人” にとっては、報われにくい仕組みだとも言えます。
語弊を恐れずに言うと、頑張らない人の方が得とさえ思えるのです。

誇りを持てる仕事をしているか
大きな組織では、ひとりひとりの仕事が“全体の成果”に埋もれがちです。
- あの人より効率的に業務を進めているはずなのに──評価は同じ?
- 新しい提案をいくつもしてきたのに──本当に伝わっている?
そんな疑問が頭をよぎることはありませんか。
組織が大きくなるほど自分の貢献度は見えにくくなっていきます。
だからこそ大切になるのは、**「この仕事にプライドを持てているか」**という問い。
外からの評価に左右されず、自分自身が誇りを感じられるかどうかが、その組織で働き続けるモチベーションになります。
私が実際に選んだ道

私がアーリーリタイアを決断をした理由は、
**「昇進すれば責任は増えるのに、やりがいは減り、給与待遇は頭打ちになる」**という虚しさからでした。
- このまま歳を重ねたとき、自分は納得できる人生を歩んでいるのだろうか?
- このまま昇進した10年後の自分は疲弊しているのでは?
- 組織に懸けているエネルギーを自分のためだけに使ったらどうなる?何とかなるのでは?
──そう自問し続けた結果、外に出てみる選択をしました。
ライフスタイルを追求する
💡リタイアはお金の問題だけではなく、ライフスタイルそのものの問題だと実感しています。
『JUST KEEP BUYING』(18万部突破のビジネス書/リンク先楽天BOOKS)でも、退職後に大切なのは「心身の健康」や「人とのつながり」であり、むしろ多くの人にとって“暇を持て余すリタイア生活”は想像以上に退屈だと警鐘を鳴らしています。
だからこそ、**「なぜ辞めたいのか」「辞めたあと何を大事にして暮らしたいのか」**を問い続けることが必要です。
私の納得
私はその問いに向き合った結果、早期退職を選びました。
FXを中心に収入を確保しつつ、自由な時間を得られたことで──
- 人間関係のストレスから解放された
- 自分のペースで働けるようになった
こうした実感が、今の自分にとって大きな幸せです。
結局のところ、大事なのは「納得できる生き方」なのだと思います。
👉 関連記事:退職後の生活は楽園?それとも後悔?

「今の自分に合う場所」は、自分で見つけに行ける
もし、今の働き方に違和感があるなら。
もし、もっと自分の能力を活かせる場所がある気がするなら──
その気持ちを無視せず、一度「自分の市場価値」を知ってみるのも一つの方法です。
自分の市場価値を知る
🟢 \公開求人で相場を知る/
👉 ハローワークを検索(無料)
🟢 \あなたの経験・スキル、いくらの価値がある?/
👉 ミイダスで市場価値をチェックする(無料)(PR)
🟢 \非公開求人に出会えるチャンス/
👉 リクナビNEXTで転職情報を見る(PR)
転職するしないに関わらず、
「他にも選択肢がある」と知ることが、不思議と心を軽くしてくれます。
“好き”を磨き、未来を育てる
転職するしないに関わらず、自分の”好き”は自分の強みになります。
忙しい時こそ、自分の”好き”を見つめ直す時間が自分自身を癒してくれます。
そして、その”好き”がチカラに変わったそのとき、独立のチャンス到来です!
組織の評価から解放されたあとに残るのは、結局“好きなこと”。それを磨き続ける時間が、未来の可能性を育ててくれるのだと思います。
まとめ

- 大切なのは、「自分が納得できるかどうか」。
- 誰かの評価ではなく、自分の声を信じる勇気が、次の一歩を導いてくれます
そして、制度や組織に守られるよりも、自分の納得を積み重ねることこそが最大の保障になる──それが、私の実感です。
▶︎次回予告
第5回:(予定)公的保障はここまで使える|「制度」を使いたおそう
※この記事は、コラム連載【辞めても大丈夫のつくり方】の一部です。