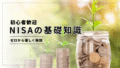資産形成を始めたいと思ったときに、まず気になるのが「NISA」と「iDeCo」。
どちらも税制優遇を受けられるお得な制度ですが、実は役割やメリット・デメリットが大きく異なります。
本記事では、FP資格を持つ筆者が、両制度の特徴を比較しながら「どっちが得か?」「どう選ぶべきか?」をわかりやすく解説します。
NISAとiDeCoどっちがいい?結論:目的と使い道で選ぼう
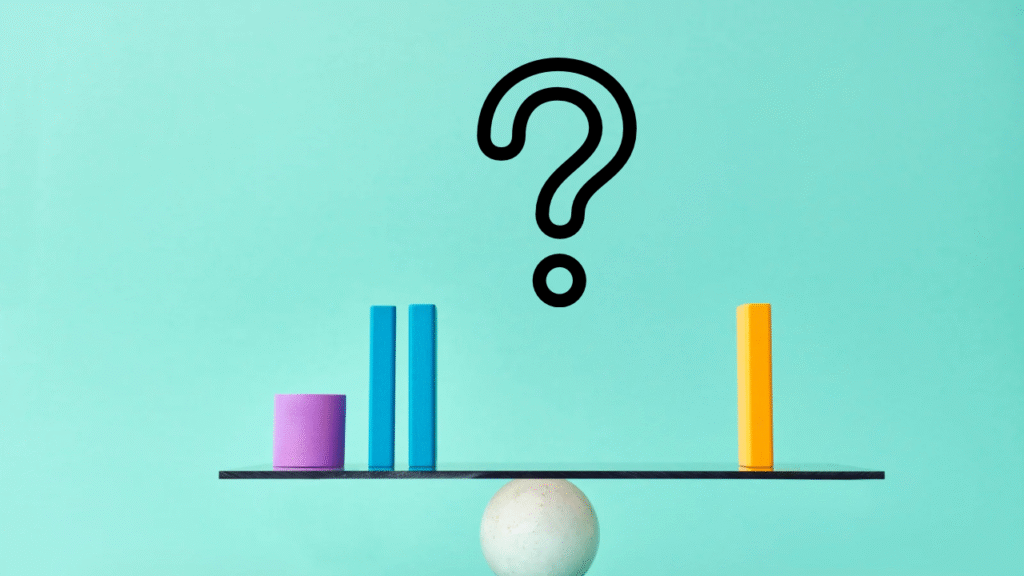
ざっくり言えば、
- 「節税しながら老後資金をコツコツ貯めたい」→ iDeCo
- 「自由に出し入れしながら将来に備えたい」→ NISA
という選び方がおすすめです。
それぞれの制度にはメリット・デメリットがありますので、目的やライフスタイルに合わせて選びましょう。
iDeCoとは?老後のための“自分年金”をつくる制度
iDeCo(イデコ)は、個人型確定拠出年金と呼ばれる私的年金制度です。
20歳以上65歳未満の公的年金加入者が加入でき、毎月一定額を積み立てて、60歳以降に受け取ります。
2025年6月の年金制度改正法成立により、加入年齢が70歳に引き上げられ、金額も改善されました。特に公務員や企業年金加入者は従来の2.3万円から6.2万円に増額となっています。
【メリット】
- 掛金が「全額所得控除」になり、節税効果バツグン
- 運用益も非課税
- 受け取り時にも退職所得控除や公的年金等控除あり
【デメリット】
- 原則60歳まで引き出せない
- 投資商品の選択肢がやや少ない
老後の資産形成を目的とした制度なので、使途が決まっていない余裕資金での運用がおすすめです。
NISAとは?誰でも始めやすい非課税投資制度
NISA(ニーサ)は、投資で得た利益に税金がかからない制度です。
2024年の制度改正で、非課税期間が無期限となり、利用しやすさが大きく向上しました。
【メリット】
- 株式や投資信託の運用益が非課税
- いつでも引き出せる自由さ
- 積立投資枠と成長投資枠で、幅広い商品に投資可能
【デメリット】
- iDeCoのような「所得控除」はない
- 投資額の上限がある(年間360万円まで)
気軽に始められ、自由に使えるお金でコツコツ増やしたい人にぴったりです。
【比較表】iDeCoとNISAの違いまとめ
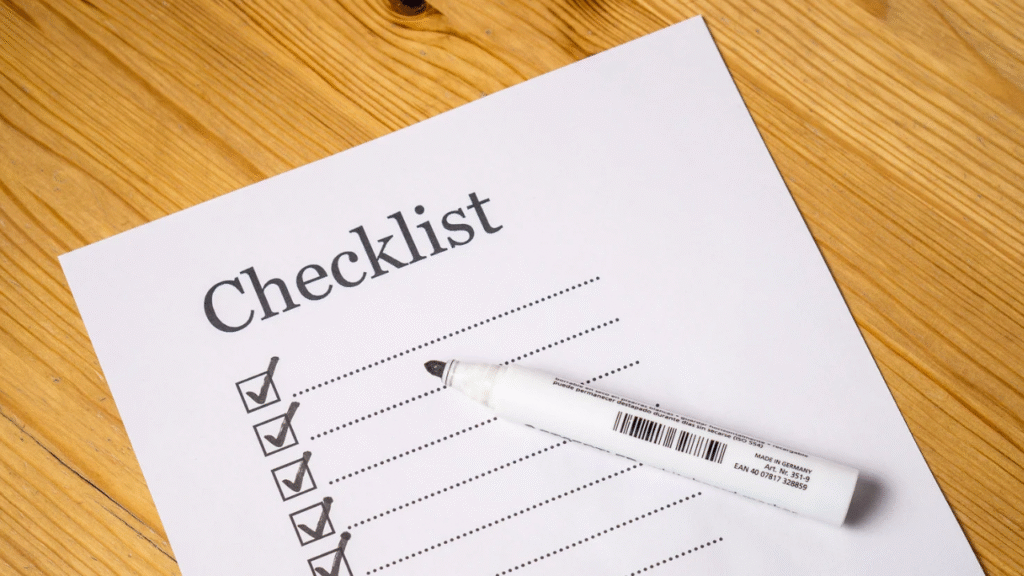
| 比較項目 | iDeCo | NISA(2024年以降) | |
|---|---|---|---|
| 現行 | 2025.6法改正、3年内に施行 | ||
| 加入可能年齢 | 20歳〜65歳(公的年金加入者) | 20歳〜70歳(公的年金加入者) | 18歳以上 |
| 投資可能期間 | 加入から60歳まで | 加入から70歳まで | 恒久(ずっと) |
| 投資上限額 | 月額2万~6.8万円(職業により異なる) | 月額2万~7.5万円 ※公務員は2万→6.2万と大幅増 | 年間360万円(積立120万+成長240万) |
| 商品の自由度 | 金融機関により異なる(元本確保型が多い) | 金融機関により異なる(元本確保型が多い) | 投資信託・ETF・株式(成長枠) |
| 資金の引き出し | 原則60歳以降 | 原則60歳以降 | いつでも可能 |
| 税制優遇 | 所得控除・運用益非課税・受取時も控除あり | 所得控除・運用益非課税・受取時も控除あり | 運用益が非課税のみ |
| 確定申告 | 必要な場合あり | 必要な場合あり | 原則不要 |
NISAの積み立て投資枠では金融庁の選定した投資信託・ETFが対象になりますが、成長投資枠では個別株式や一部を除く投資信託に投資が可能です。
一方、iDeCoでは、金融機関によって異なりますが、一般的には元本確保型の保険商品や定期預金、元本変動型の投資信託がラインナップされています。
新NISAとiDeCoで運用できる金融商品は、金融機関の取り扱い商品によって異なります。
iDeCoとNISAは併用もできる!筆者の使い分け方
「iDeCoとNISA、どちらか1つを選ばないといけない?」
そんなことはありません。併用可能です!
私も併用中で、以下のように使い分けています。
- iDeCo:自分年金として割り切り、毎月定額を積立(60歳まで楽しみに寝かせておく)
- NISA:日々の家計から少額をコツコツ積立(資金が必要になったら引き出しOK)
制度の併用で、ライフステージに合わせた柔軟な資産形成が可能になります。
結局どっちを選ぶべき?タイプ別おすすめ

以下のような基準で選ぶとわかりやすいです。
- 今すぐ使うかもしれないお金 → NISA
- 節税しながら老後資金を貯めたい → iDeCo
- 両方活用できる余裕がある → 併用が最強!
まとめ:違いを知って、自分に合った制度を選ぼう
iDeCoもNISAも、「運用益が非課税」という点では共通していますが、控除の有無や引き出し自由度など大きな違いがあります。
大切なのは、「今のお財布事情」と「将来の使い道」に合わせて選ぶこと。
無理せず、少額から資産形成を始めてみましょう!
初心者の方の参考になれば幸いです。
\NISAデビューにおすすめ!/
✅【SBI証券】公式サイトはこちら
✅【楽天証券】公式サイトはこちら
\iDeCoデビューにおすすめ!/
✅【SBI証券】公式サイトはこちら
✅【楽天証券】公式サイトはこちら